
新しい生き物たち2026年02月09日
えのすい生まれ! かわいいフォルムのナメダンゴ展示開始!

新しい生き物たち2026年02月05日
「ノドグロ」でお馴染み 「アカムツ」展示中

新しい生き物たち2026年02月02日
冬の妖精「クリオネ」展示中!

新しい生き物たち2025年12月30日
ハート型を見つけたらラッキー!
南国生まれのミズクラゲ「ナンヨウミズクラゲ」展示開始
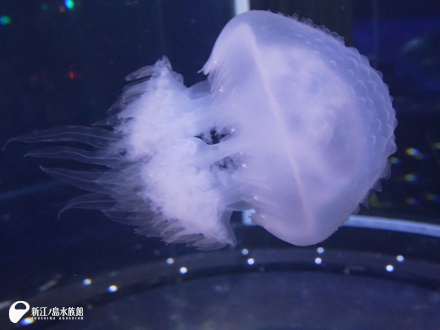
新しい生き物たち2025年12月30日
もふもふの傘を持つクラゲ「ミノクラゲ(蓑水母)」展示!

新しい生き物たち2025年11月29日
えのすい生まれ 日本初展示
カリブ海周辺に生息する黄色いサカサクラゲの仲間
「カシオペア・フロンドーサ」 展示開始

新しい生き物たち2025年11月21日
岩上のお花畑にご用心!
「イラモ(ポリプ)」展示開始!

新しい生き物たち2025年11月15日
まるでクリスマスイルミネーションの点滅のよう?
「シリヤケイカ」展示開始
